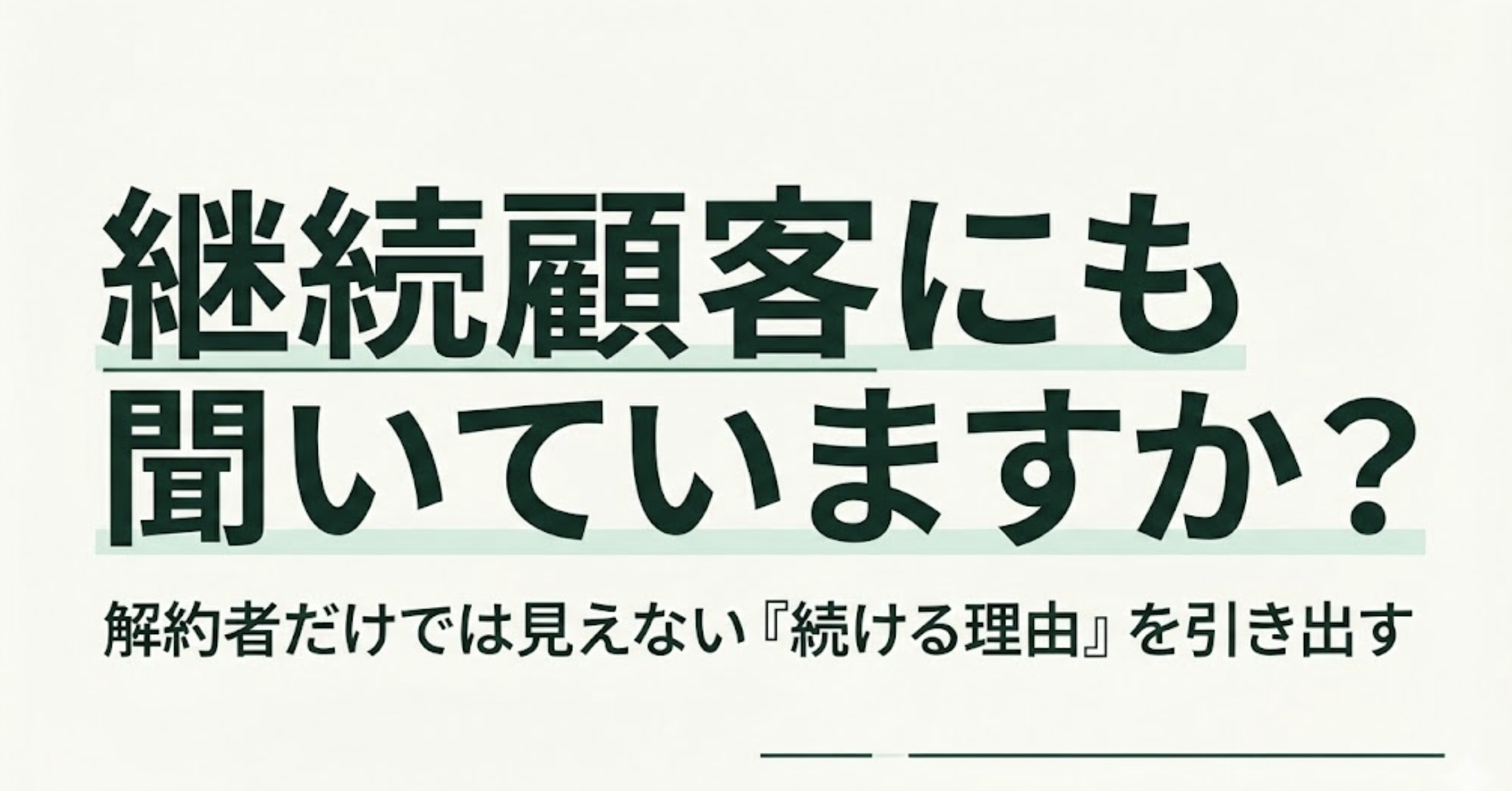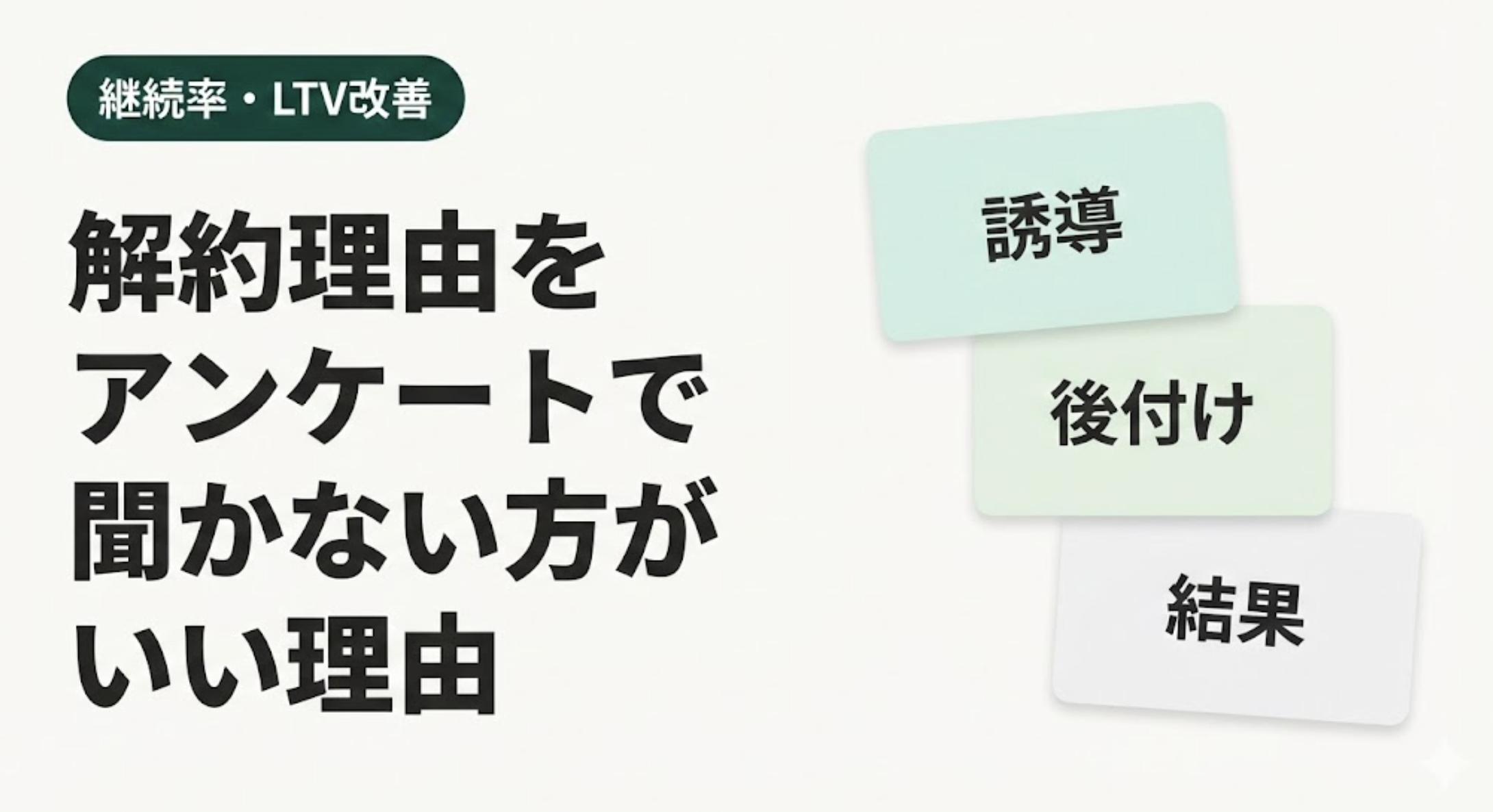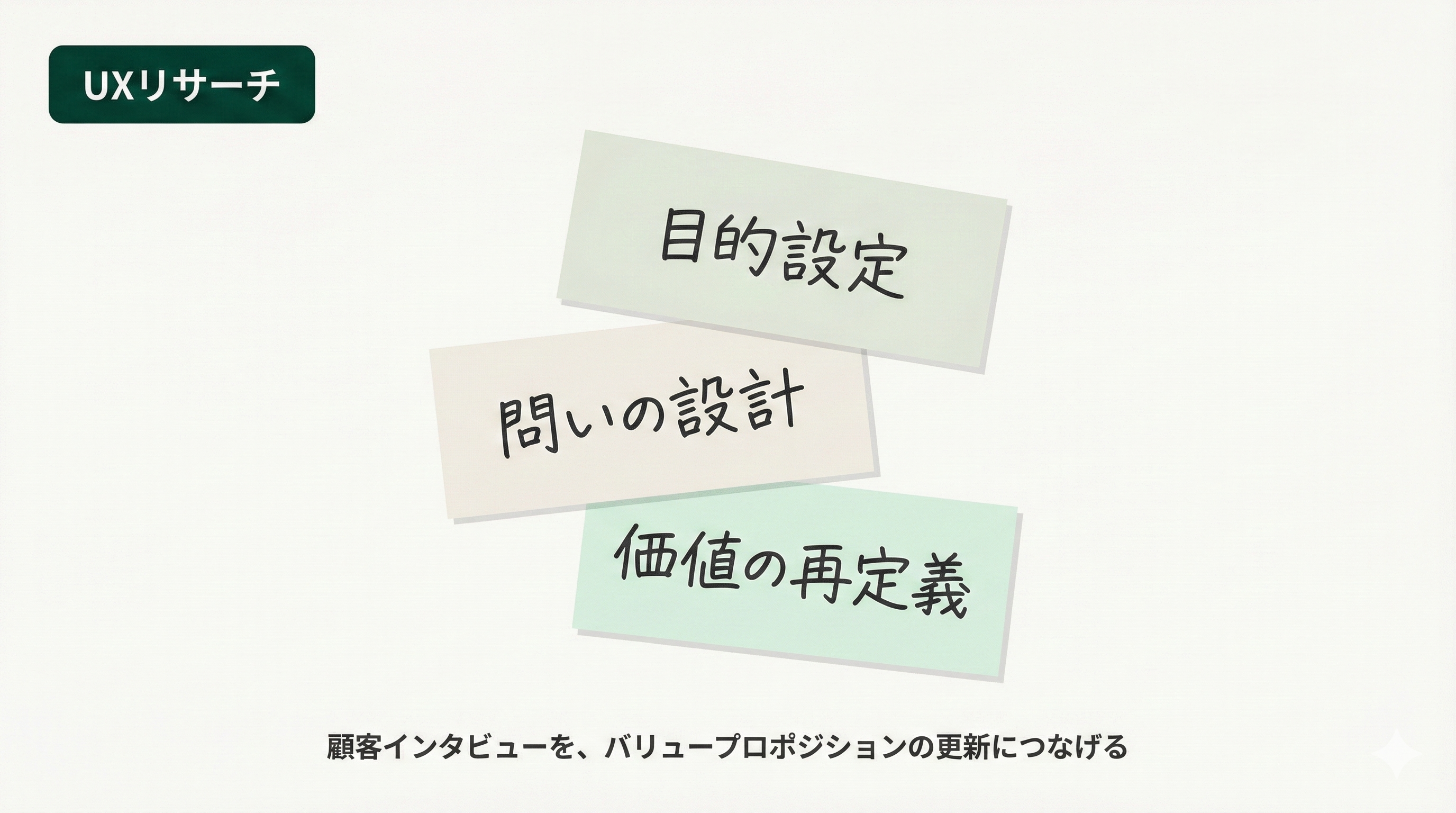目次
相談するBtoCの事業会社でユーザーインタビューをどう実施するか。BtoBの企業ではビザスクなどのスポットコンサルを使い、1回数万円以上の謝礼を払ったり、自社の顧客向けにインタビューを実施したりすることが多いと思います。BtoCの事業会社のユーザーリサーチではどのようなアプローチを取ることが多いのでしょうか?
本記事では、実際に20代から70代まで幅広いユーザーへのインタビュー経験を基にBtoC事業会社における効果的なユーザーインタビューの実践方法を解説します。
既存サービスがある場合の基本アプローチ
ユーザーへの打診方法
既存ユーザーがいるサービスの場合、以下の方法で比較的簡単にインタビュー対象者を集められます。
- アンケート経由での募集:サービス内アンケートで協力者を募る
- 直接打診:メールやアプリ内通知での個別連絡
- セグメント別アプローチ:特定条件のユーザーに絞って打診
重要なのは、闇雲に全員に声をかけるのではなく、インタビューの目的に応じて適切なユーザーを選定することです。
謝礼設計の考え
謝礼の要否はユーザーの属性と商材によって大きく異なります。
無報酬でも協力が得られるケース
ロイヤリティの高いユーザーは、「運営と話せること」自体に価値を感じ、サービス改善のアイデアを共有したいという動機から無償でも協力してくれることが多いです。ただしこうしたユーザーからは批判的な意見が出にくく、好意的なフィードバックに偏る傾向があることを認識しておく必要があります。
謝礼が必須となるケース
- 解約済みユーザー
- ライアル後に離脱したユーザー
- 利用頻度が低下しているユーザー
これらのユーザーはサービスへの関心や熱量が低下しているため、Amazonギフト券3,000円〜5,000円程度の謝礼なしには協力を得られないことがほとんどです。しかし率直な改善点や離脱理由を聞くことができる重要なチャンスであり、インサイト回収のための投資として割り切って臨みたいです。なお、解約顧客と継続顧客では聞くべき質問が異なります。詳しくは「継続顧客と解約顧客、インタビューで聞くべき質問の違い」で解説しています。
新規事業の場合のアプローチ
リサーチツールを活用した定量調査
まだユーザーがいない新規事業の場合、以下のステップで進めます。
1. 定量調査の実施
- Quiqumo、ユニーリサーチなどのリサーチツールを活用
- 最低料金1,2万円程度から実施可能
- 1週間程度で数百件のアンケート回収が可能
2. セグメント特定
- 定量データから仮説を検証
- ターゲットセグメントを明確化
3. 定性調査への展開
- 特定したセグメントに近い人物を探す
- 知り合い経由やSNSなども活用
スクリーニング設計〜持続可能な仕組みを意識する〜
中長期で反応率を守ることが重要
ユーザーインタビューは一度きりではなく継続的に実施すべき活動です。そのため以下の点に注意が必要です。
やってはいけないこと
- 全会員への一斉送信
- セグメント未設定での乱発
- 反応率を考慮しない過度な募集
おすすめの動き方
1. 初回実施時に反応率を測定し、基準値を把握
2. 必要人数から逆算して送信対象数を決定
3. セグメントを可能な限り絞り込む
4. 最重要ターゲットには「○○様へ」という個別メールも検討
反応率の管理を怠ると候補を刈り取り切ってしまって次回以降の募集効果が著しく低下し、将来の自分を苦しめることになってしまいます...。
打診メールの書き方:自分ごと化を促す技術
参加のハードルを下げる文面設計
多くのユーザーは実際の打診文を手にとっても、「まさか自分が対象になるはずがない、他のガチ勢のユーザーが対象なのだろう..仮にやるとしても1時間も話せるわけない」と考えがちです。すれ違っています。すれ違いを防ぐような文言の工夫を施すべきです。
効果的な文面例
- 「現在ご利用に至っていないユーザー様を対象にご連絡しています」
- 「サービス利用の多寡に関わらず、お気軽にご参加ください」
- 「45分から1時間弱程度でお話を伺えれば幸いです」
時間表記についても、「1時間」だと少しハイカロリーだと身構えられ、「30分」では聞きたいことが網羅できず、不十分に終わる可能性があります。「45分から1時間弱」という表現が、心理的ハードルを下げつつ、必要な情報を収集できる最適なバランスだと考えています。
オンライン実施を推奨する理由
機会損失を防ぐ実施形式
ユーザビリティテストなど特殊な場合を除き、基本的にオンライン実施を推奨します。
オンラインのメリット
- 参加ハードルが低く、幅広いユーザーから意見収集可能
- 地理的制約がない
- スケジュール調整が容易
オフライン限定のデメリット
- 熱量の高いユーザーに偏る
- サイレントマジョリティの声を拾いにくい
- 機会損失が大きい
ユーザーの属性理解や購買理由の解像度向上といった目的であれば、オンラインで十分な成果が得られると思います。
BtoCでのユーザーインタビュー特有の課題と対策
前日リマインドは必ず行う
BtoC事業では、BtoB事業と比較して以下の理由でドタキャン率が高くなります。
以下のような理由で全然ドタキャンが起こり得ます。ドタキャン起こる前提で、そのリスクを少しでも下げられるように、という発想で配慮を行うと良いと思います。
- 仕事の都合による急な予定変更
- うっかり忘れ
- 優先順位の変化
これらを防ぐため、前日(と当日の)リマインドは必須です。面倒に感じるかもしれませんが、実施率を大幅に改善する重要な施策です。
日程調整ツールの活用
推奨ツール
- Spir、TimeRex、アイテマスなど(日本語表記・リマインド機能が付随するサービスが望ましい)
- 自動リマインド機能付きを選択
よくある誤解への回答
「日程調整ツール使うには、ITリテラシーが必要では?」という懸念がありますが、Zoom/Google Meetを使えるユーザーであれば、日程調整ツールも問題なく利用できます。むしろ、日程候補をメールで羅列する方が混乱を招きやすいです。
意外にも細かいtips(配慮)の積み重ねが成果を生む
以下の「細かい技術」が、インタビュー実施までの期間短縮、成約率向上につながります。
1. データの蓄積と活用
- セグメント別の反応率データを記録
- 募集文面のA/Bテスト実施(入魂の文章感が出たほうが望ましい場合や、ドライである方が反応が良い場合など、属性によって違いがあることが多い)
- 最適な曜日・時間帯の把握
2. プロセスの最適化 - テンプレート化と社内共有を徹底(勝ち筋の打診文が、共有されず、属人的な文章がそれぞれ使われているケースが非常に多い)
- リマインドのタイミング調整
- フォローアップの仕組み化
これらの積み重ねにより、募集から実施まで1-2週間かかっていたプロセスを数日に短縮することが可能です。
まとめると?
BtoC事業会社のユーザーインタビューは、ToBのインタビューとはかなり作法や心構えが異なると考えられれます。重要なのは以下の3点です。
1. 持続可能な仕組み作り:反応率を維持しながら継続的に実施
2. 適切な謝礼設計:ユーザー属性に応じた柔軟な対応
3. 参加しやすい環境:オンライン実施と日程調整ツールの活用
フットワーク軽く、継続的にユーザーの声を聞く仕組みを作ることが、プロダクト改善の第一歩となります。
インタビュー当日の進行や、記録、社内への展開や知見の抽出の仕方についても記事を改めて詳しく解説予定です。質問設計から分析手法まで、実践的なノウハウをお伝えします。
また、解約率改善を目的としたインタビューでは、継続顧客と解約顧客で聞くべき質問が異なります。「継続顧客と解約顧客、インタビューで聞くべき質問の違い」も合わせてご覧ください。
インタビュー当日に使える小技は以下の記事で紹介しているのでこちらもぜひご覧ください。
.jpg)